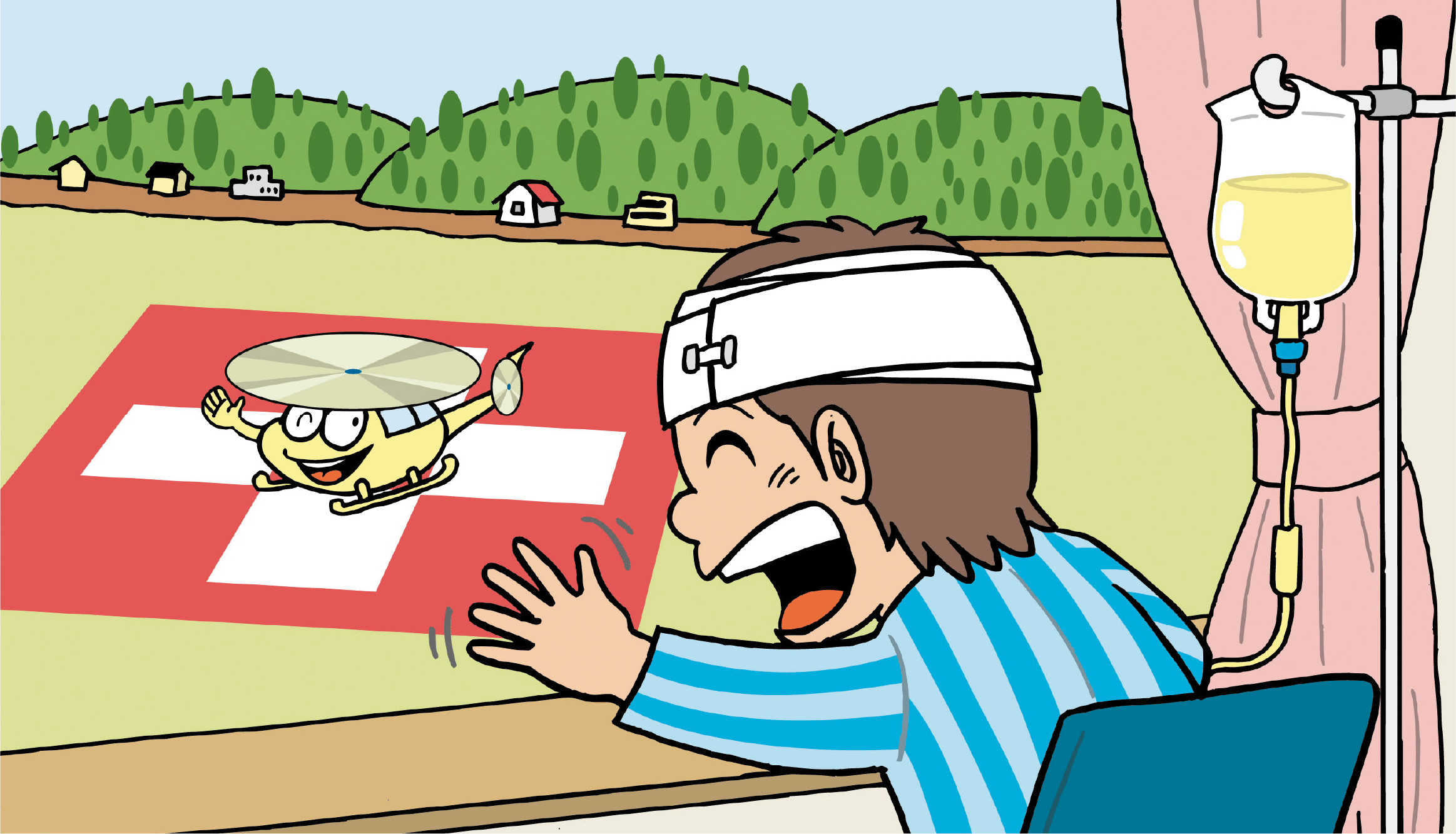コラム
ヘリポート業界の動向、知識などの情報を記事にしています。
「新・ヘリポートの造り方」
2025.05.07
「残念なヘリポート」が出来上がってしまう理由 その3
腰が重い「運輸省」と「建設省」、対応が後手にまわらないか
このコラムではヘリポート建設に関するおかしな点や危険な点をいくつか指摘しました。
病院の着陸帯には病院ヘリポートマークを描くべきなのに、そこが「緊急離着陸場」や「非公共用ヘリポート」である場合には病院ヘリポートマークを描けない矛盾。本来なら「緊急離着陸場の構造」に対しては「場外申請」に許可を出すべきではないのに、最近は許可されるケースがあること。また敢えて触れませんでしたが、「原発敷地内の着陸帯と農薬散布のための畑の中の着陸帯が同一の判断基準で許可されるのはおかしい!」とかねてから私は主張しています。
これらの矛盾を「運輸省」や「建設省」の役人に伝えたことは何度もあります。いずれについても「仰せの状況があることは確かに確認できました。検討します」との答えをいただいていますが、それきりです。なかなか直るものではないようです。対策を講じるためには、世論の後押しなど、きっかけが必要なのでしょうか。やはり、事故が起きてからではなく、常日頃から安全行政を徹底してほしいものです。
履き違えた「特例」の意味
航空法第81条の2に「捜索または救助のための特例」が定められています。捜索や救助のためならば事前に申請を出していない(着陸許可を得ていない)場所に着陸しても構わない、というものです。最近はこの特例が拡大解釈され独り歩きし始めています。安全上非常に困った問題です。
以前にこんなことがありました。地方の病院屋上ヘリポート建設に際し当社が航空コンサルティングを請け負いました。コンサルティングの一環で、その県の防災航空隊を訪ねたときのことです。大きさや進入ルートの確認に伺ったのですが、防災航空隊のパイロットが「大丈夫ですよ。うちは『特例 』で降りますから」と答えたのです。
ヘリポートを造る施主からすると、とてもありがたい言葉です。「いろいろと気にしなくてもいいですよ」と言ってもらったようなものです。最近はドクターヘリのパイロットでも同じことを言う方が出てきました。施主からすると規制が緩くありがたい面もあるのですが、これでは数年後に着陸帯の不備を原因とする事故が発生しかねません。「特例」はあくまで特例であって、普段から「特例で降りる」などという考えは持つべきではないでしょう。ICAOの基準に沿った恒久的な安全が保障される着陸帯を造るべきです。