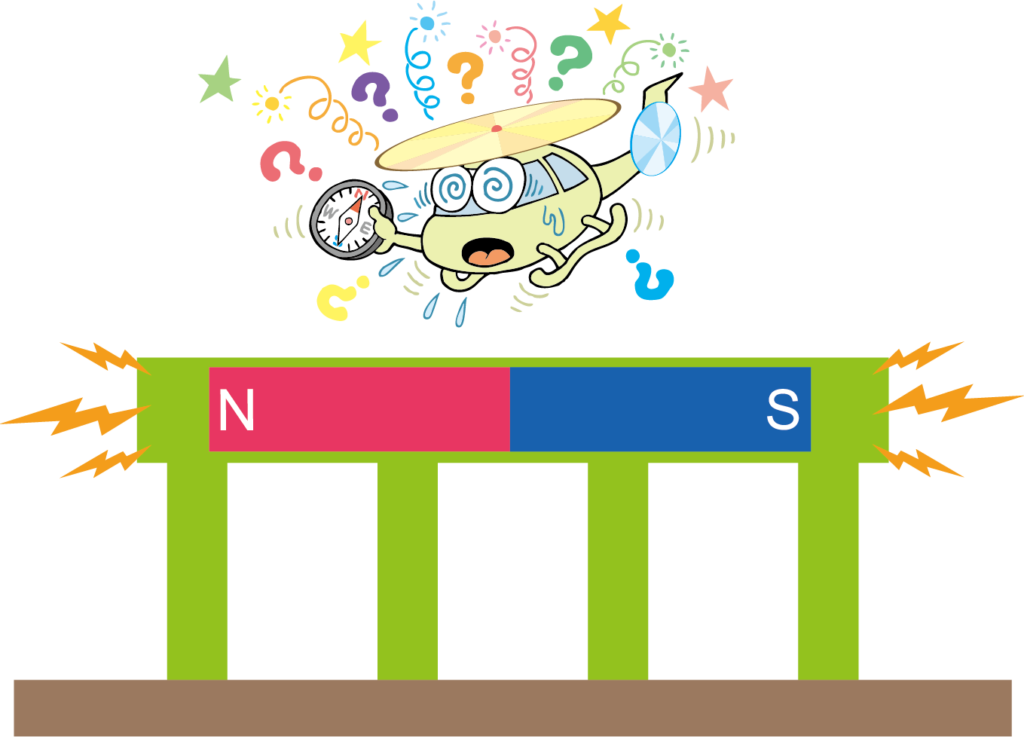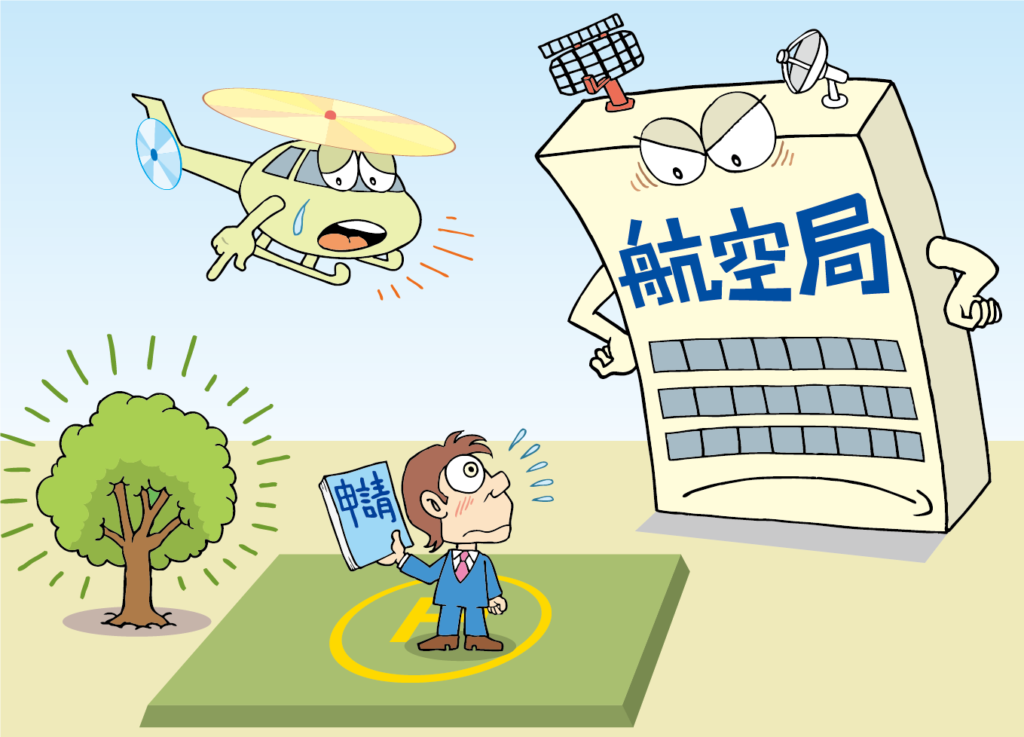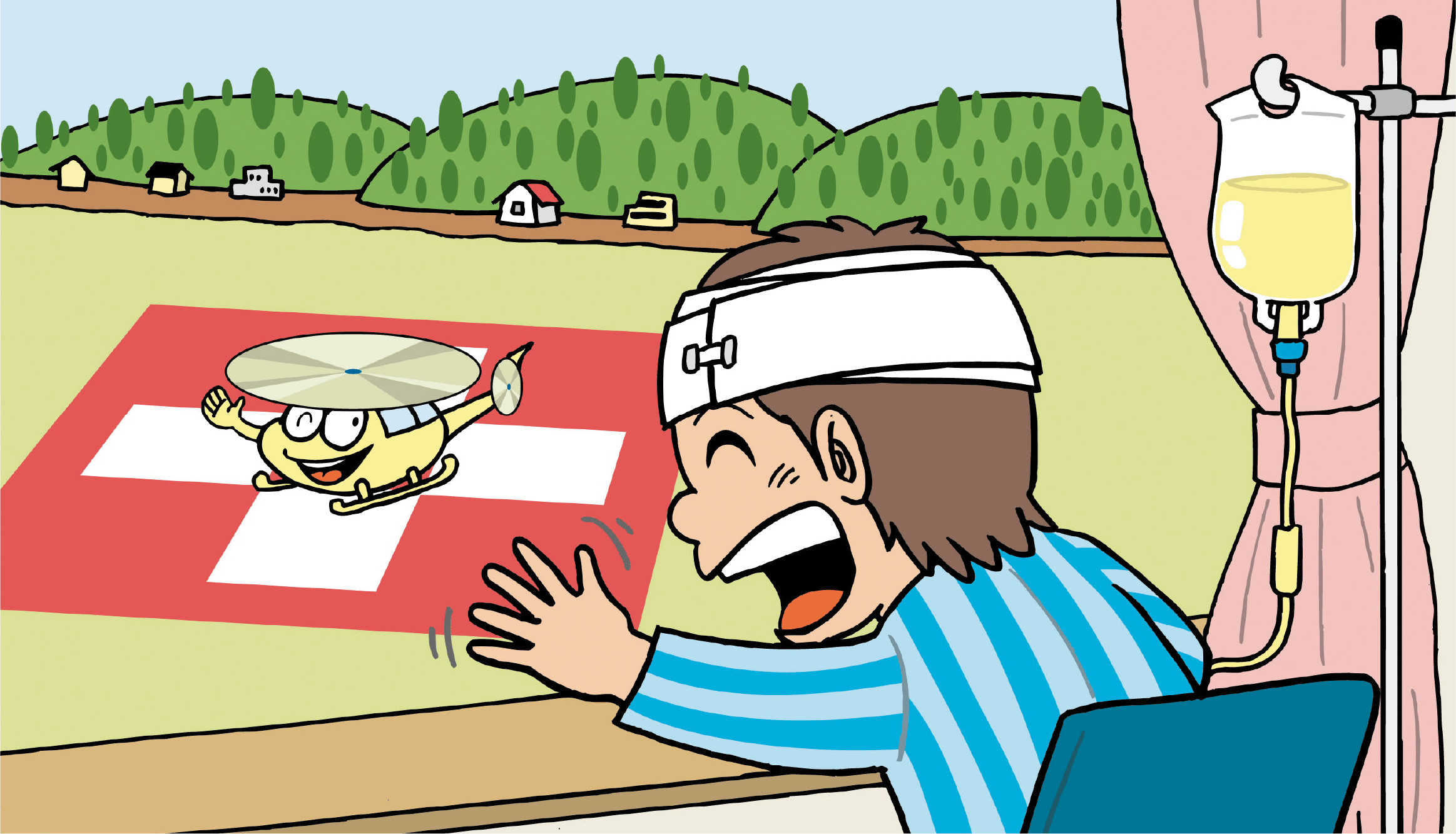コラム
ヘリポート業界の動向、知識などの情報を記事にしています。
「新・ヘリポートの造り方」
2025.07.03
施主・設計者・運航会社が気をつけることと、航空局に望むこと 【その2】
◾️前回のコラムはこちら→ 施主・設計者・運航会社が気をつけることと、航空局に望むこと 【その1】
運航会社(場外着陸許可申請者)が気を付けるべきこと
少しでも「危ないかな?」と思ったら「飛行場外離着陸許可申請」をしないことです。場外離着陸場で事故があると、運航者の責任になることがあります。運航者は十分に注意して「場外申請」を行いましょう。飛行障害につながり兼ねない項目や着陸帯の大きさなどのチェックだけでなく、以下のことも入念に確認して「場外申請」を行いましょう。
1【着陸帯表面がきちんと防水されているか。防水層が破れていないか】
本書でも繰り返し指摘しましたが、防水されていないコンクリートは日々劣化が進みます。設計段階では十分な強度があっても、10年、20年と経つと強度が落ちていきます。表面が防水されていない屋上ヘリポートは場外申請を控えるべきです。防水層が破れている場合は速やかに補修をお願いするべきです。
2【磁界に乱れはないか】
着陸帯の磁界が乱れているとヘリコプターの計器が狂うことがあります。大変危険です。屋上ヘリポートではしばしば、使用している鉄筋が原因と思われる磁界の乱れが報告されています。磁界に乱れがある着陸帯は場外離着陸場には適しません。
航空局に望むこと
ドクターヘリの普及に伴いランデブーポイント(臨時離着陸場)のための「場外申請」が急増しています。ランデブーポイントは、救急車で運ばれる傷病者を、ヘリポートに乗せ換える場所で、多くは各運航者からの包括申請や継続申請で処理されているようです。やむを得ない状況であることは理解できますが、せめて屋上の場外離着陸場や利用頻度の高いランデブーポイントは定期的に細かくチェックしてもらいたいものです。樹木が伸びたり新しい建物が建ったり、最初に場外申請した頃とは周りの状況が一変した場所でも、継続申請では気づくことができません。特 に 屋 上 の 場 外 離 着 陸 場 で は「 構 造 」「 防 水 」「 磁 気 の 影 響 」な ど のチェックを申請者にお願いするべきでしょう。防水層の破れはないか、コンクリートの劣化はないかなどのチェックも重要です。航空局から運航者に対し「着陸を断る勇気を持て」と指導することも大切でしょう。「事故が起こったらそうします」ではダメなのです。事故が起こってからでは遅いのです。