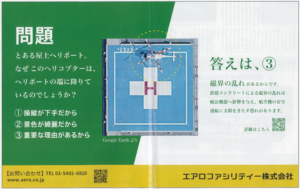News & Topics
エアロファシリティーからのお知らせです
お知らせ
2025.08.01
徳島県鳴門病院ヘリポートが病院新聞トップ記事で取り上げられました
弊社が設計・施工・コンサルを行った徳島県鳴門病院ヘリポートについて、このたび病院新聞の一面トップ記事にて取り上げられました。
同新聞には弊社のカラー広告も掲載しています。
※竣工式とヘリポートの詳細は弊社の[ニュース]でもご紹介しているので、併せてご覧下さい。
以下記事本文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
南海トラフ巨大地震を見据え 災害対応と救急医療を強化
フェーズフリーの考えに基づくヘリポートを設置
徳島県鳴門病院(徳島県鳴門市、307床)はこのほど、徳島県鳴門災害対策施設(ヘリポート)の運用を開始した。同施設は、フェーズフリーの考えに基づき、南海トラフ巨大地震などの大規模災害を見据えた災害医療と平時の救急医療に対応した機能を担う。当初は、ヘリポートとともに病院を津波から守る防潮壁を同時に整備する計画だったが、国による津波被害の想定が見直されたことを受けて、ヘリポートの設置を先行して整備。自衛隊ヘリも離着陸可能なヘリポートや備蓄倉庫、DMAT隊員待機室なども備え、平時は院内の会議や研修、地域住民への説明会にも使用する。フライトドクターの経験もある同院の住友正幸理事長兼病院長は、「平時から使えないものは、災害時も使用できない」と話し、訓練などソフト面の取組みを充実させるとともに、ヘリポートが整備されたことにより安全面の強化が図られる効果に期待を寄せる。特に救急・災害医療の現場では、緊迫した状況下で医療スタッフも緊張を強いられる中、「より患者に意識を向けられるようになる」と語った。住友理事長兼病院長にヘリポート設置の意義などを聞いた。
徳島県鳴門病院は、高知県から徳島県に流れる吉野川の北岸で唯一の災害拠点病院で、徳島県北部を中心に、香川県東部や兵庫県淡路島地域を診療圏域としている。しかし、吉野川北岸にはこれまでヘリポートがなく、喫緊の課題となっていた。ヘリポートの設置は同院が「県北部唯一の災害拠点病院の使命を果たすために必要不可欠」だった。 同院はこれまで、近隣の運動公園をドクターヘリと救急車が合流するランデブーポイントとしていた。そのためヘリコプターの離着陸時に発生する砂塵の飛散防止のため、救急車の他に消防隊が急行し散水する必要もあった。「私もフライトドクターとして飛んでいたが、グラウンドのような場所に離着陸するのは、パイロットも気を遣う」と話す。「とくに災害時はヘリに搭乗する人のテクニカルな面からも安全なヘリポート施設が必要」と指摘。ドクターヘリの機内では、緊迫した状況の中でフライトドクターとナースが話し合いながら適切な処置を施しており「着陸する場所が安定していることで、意識や視点の多くを患者に向けられる」と話す。
患者の搬入・搬出とランデブーポイントに
徳島県鳴門病院災害対策施設(ヘリポート)は、 同院の外来駐車場内に今年5月末に竣工した。建物構造は鉄骨造4階建て、延床面積1063.18㎡。病院本館と 3、4階の渡り廊下でつながっている。上下階はエレベータと階段で移動する。1階にはドクターヘリによる患者の搬入・搬出と、ランデブーポイントとして使用できる救急車の待機スペースや受入れホールを設けたほか、自家用発電機などを設置している。
平時は会議室や地元住民説明会に活用も
2階には倉庫を、3階には備蓄倉庫とDMAT隊員待機室を設けている。備蓄倉庫は災害時に使用する医薬品を備蓄するため室温を25℃以下に管理。病院本館の地下にある薬局がダメージを受けてもサテライト薬局を展開できるようにしている。そのほか食料品、衛生材料、透析用機材・薬液・携帯トイレなどを備蓄。備蓄品の劣化を防ぐため窓には遮光フィルムを施している。DMAT隊員待機室には、100インチのモニターを設置し、壁にはプロジェクターのスクリーン仕様の壁紙を施工している。同院の災害医療センターの執務スペースとして、映像を投影しながら、ウェブ会議や情報収集・分析などもできるようにした。 医療ガスのアウトレットも2カ所設け、多数の傷病者が発生した際、搬出するまでに患者を一時的に収容するスペースにも充てる。平時では、院内の会議や研修、地元住民への説明会のスペースとして活用するなど、ハード面でもフェーズフリーの観点を取り入れている。
軽量で劣化しにくいアルミデッキ製に
4階のヘリポートは、 軽量で劣化しにくいアルミデッキ製。ヘリポートの設計・施工を手掛けるエアロファシリティ (東京都港区)が施工した。建物の荷重を減らすことで地震の揺れにも耐えやすく、離着陸時に発生する吹き下ろす強い風 「ダウンウォッシュ」によるコンクリート片などの飛散による被害を防止できる。着陸帯の面積は約441平方㍍で、高さ約15㍍に位置している。 耐荷重は12㌧で、ドクターヘリや消防ヘリに加えて自衛隊の中型ヘリも離着陸が可能だ。ヘリポートに設置された風向計などの数値はドクターヘリの基地局を通 じて搭乗者が確認でき、 着陸時は「機長がヘリポートの吹き流しを見ながら着陸できる。非常に安全なシステムだ」と住友理事長兼病院長は信頼を寄せる。運用面でも「いままでランデブーしにくかった」が、例えば「当院から徳島県立中央病院や徳島医療大学病院に搬送すれば、ヘリポートに直結した手術室やICUに患者を迅速に搬送できる。 患者の受け入れ・搬送から処置までの時間が大変短くなる。」と救命率向上にもつながると指摘。「単純に搬送するだけではなく、医療がどこから始まって、どのように連携するのかを考える上でも非常に便利になる」と期待を寄せた。
地元住民ら約600人が参画した防災訓練も
「平時から使えないものは、災害時も使用できない」との考えから訓練などソフト面の取組みも拡充させる。同院は2023年に災害医療センターを設置し、職員や地元住民のボランティア、医師会などから約600人以上が参画して南海トラフ巨大地震発災後60分間を想定した防災訓練を2年続けて実施。ハードとソフトの両面の充実に取り組んできた。「今回ヘリポートができたので、地域住民に見てもらった上で、安心して当院に逃げてきてもらいたい」と話す。地域住民の避難所は病院に近接する山の上にあるが、「避難所にたどり着けな い人もいる。そうした人はまず当院に避難してもらう。助かる命は助かってほしい」と呼び掛ける。今後、防潮壁ができれば、さらにその前提で訓練を行う方針だ。
医薬品や物資搬送にドローンの活用も
今後の医療における空の利用について航空医療学会の会員でもある住友理事長兼病院長は「医薬品と物資輸送は、ドローンを活用する方向性に進む」と見込む。「特に災害時、山間部やへき地の医療機関は、地滑り被害なども想定され、陸路による搬送は困難」と指摘。地域性や交通インフラの事情にもよるが、「どこも人員が足りないため、ドローンの活用は大いにあり得る」と話す。ただ、「人の命となると、もう一段階高い安全性が要求される。ドクヘリでもまだ危険な面がある中で、 “空飛ぶクルマ”を使った患者の搬送はまだ先だろう」と予測する。今後の次世代空モビリティ―の活用については「当院だけでなく、県など広域 的な取組みとして進められるべきだろう」との考えを示した。
病院新聞 第2855号(2025年7月31日発行)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
同じカテゴリの記事
各種資料請求・お問い合わせ等ございましたら、
お気軽にご連絡ください。(平日9時~17時)
- 総務部(代表)
- 03-5402-2555
- ファシリティー事業部
- 03-5402-6810
- 航空機事業部
- 03-5402-6884
- 防衛グループ
- 03-5402-2556